赤ちゃんの夜泣きは、親にとって想像以上に消耗する日々です。
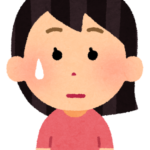
いつまで続くの?
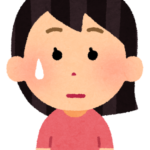
私だけが大変なの?
と不安になりますよね。
この記事では、夜泣きの年齢の目安と、筆者の家庭で実際に効果があった対策を5つ、具体例つきで紹介します。
参考になれば嬉しいです!
夜泣きは何歳まで続くの?年齢別の目安
夜泣きには個人差がありますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 〜1歳半:夜泣きが最も目立つ時期。生活リズムや発達の影響で覚醒しやすくなります。
- 2歳ごろ:言葉や感情が発達するため、一時的に夜中に起きる子もいます。
- 3歳以降:多くは減少する傾向。ただし夢や不安、体調不良で起きる場合があります。
筆者の経験では、娘は1歳頃でだいぶ落ち着き、息子は2歳近くまで断続的に夜泣きが続きました。
つまり「〇歳で必ず終わる」とは言えません。
重要なのは原因を探り、対策を重ねることです。
夜泣きの主な原因
夜泣きは複数の要因が絡み合って起こることが多いです。
代表的な原因を挙げます。
- 生活リズムの乱れ(昼寝の長さ、就寝時間のズレ)
- 発達の節目(寝返り、立っち、言語発達など)
- 環境の変化(引越し、保育園入園、家族構成の変化)
- 体調不良や不快感(鼻づまり、歯の生え始め、オムツの不快さ)
我が家で効果があった夜泣き対策5選
1. 就寝前ルーティンを固定する
「お風呂→授乳(または水分補給)→絵本→消灯」のように毎晩同じ流れにすることで、子どもが眠る合図を理解しやすくなります。
照明を少し落とし、穏やかな音楽を小さめに流すと寝つきが良くなりました。
うちではこちらをずっと使用してます↓

2. 昼間に十分に体を動かす
日中の活動量が多いと夜の睡眠が深くなる傾向があります。
公園遊びやリズム遊び、簡単な体操を取り入れて、更に昼寝は短めに調整すると効果的でした。
3. 室内環境を整える
快適な室温・湿度は睡眠に直結します。
目安は室温20〜23℃、湿度50〜60%。
遮光カーテンで外の光を遮り、ホワイトノイズや扇風機の音を弱めに流すと、物音で目を覚ましにくくなりました。
ホワイトノイズとは「ザー」というママのお腹の中にいたときにの様な音。ホワイトノイズが流れるアイテムはこちら↓

4. 起きてもすぐに抱っこしない(様子観察)
寝ぼけて短時間だけ泣くことがあります。
声が小さかったり、泣き方が断続的なら、
まずは数十秒様子を見てそのまま寝る可能性を確認します。
ただし、泣き方が強い・熱がある・様子がおかしい場合はすぐ対応してください。
5. 親の睡眠を最優先にする
親が疲弊すると対応の質も下がります。
可能ならパートナーと交代で対応する、家族や友人に短時間見てもらう、週末に昼寝をもらうなどして体力を回復しましょう。
疲れすぎた状態は長期的な育児の負担を増やします。
まとめ:夜泣きはつらいけど必ず終わる
夜泣きは個人差が大きく、「何歳まで」と断定はできませんが、
多くは3歳前後で落ち着く傾向があります。
生活リズムの見直し、昼間の活動量、環境調整、そして親の休息確保が、夜泣き対策の基本です。
完璧を求めず、
小さな工夫を重ねながら乗り越えていきましょう!
この記事が少しでも楽になるヒントになれば嬉しいです。
実践しても改善が見られない場合は、小児科や保健師に相談してください。
お住まいの自治体によっては、無料で育児相談できる窓口があるので気軽に電話で相談するのもオススメです♪




コメント